今回から100回にわたって、Linuxコマンドの説明をしていこうと思います。
記念すべき第1本目(回?)のコマンドは「ls」コマンドです。ls コマンドは、Linuxで「ファイルやディレクトリの一覧を表示する」ために使われる非常に基本的なコマンドです。
今回はls コマンドの簡単な使い方と、よく使うオプションを紹介します。
基本的な使い方
ls
このコマンドを実行すると、現在のディレクトリ(カレントディレクトリ)にあるファイルやディレクトリが表示されます。
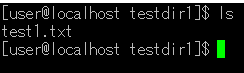
よく使うオプション
ls -a
隠しファイルも含め、すべてのファイルを表示するオプションです。
※Linuxにおける隠しファイルとは、「.」 で始まるファイルやディレクトリを指します。
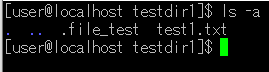
ls -l
ファイルやディレクトリの詳細情報を表示するオプションです。
各ファイルやディレクトリについての詳細情報(パーミッション、所有者、サイズ、最終更新日時など)を一覧で表示します。
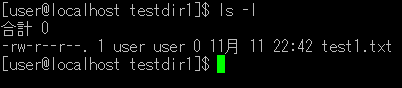
ls -h
人間に読みやすい形式でサイズを表示するオプションです。
サイズを「1K」「5M」などの単位表示するので、ファイルの大きさがわかりやすくなります(-lと組み合わせることが多いです。)
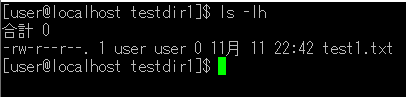
ls -R
サブディレクトリも含めて再帰的に表示するオプションです。
サブディレクトリの中身もすべて表示します。ディレクトリ構造を確認する際に便利です。
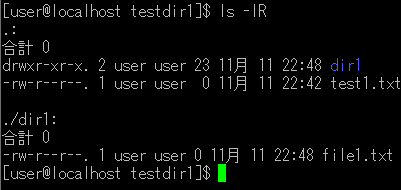
ls -t
更新日時でソートして表示するオプションです。
更新日時順にソートして表示します。新しいファイルやディレクトリが上部に表示されます。
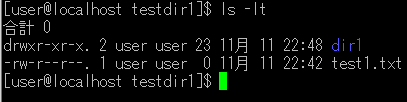
複数のオプションを組み合わせた使い方
既に上記ででてきていますが、オプションを複数組み合わせて使用することもできます。
ls -alhこのコマンドは、隠しファイルを含めてすべてのファイルとディレクトリを、詳細情報と人間に読みやすいサイズ形式で表示します。
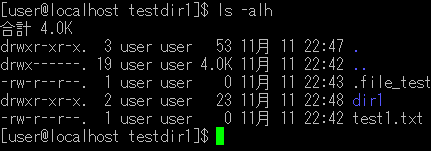
今回は以上です。


